郵便料金計器の価格帯やメーカーによる違いは?上手な選び方を紹介
郵便料金計器を導入すべき会社・企業の特徴
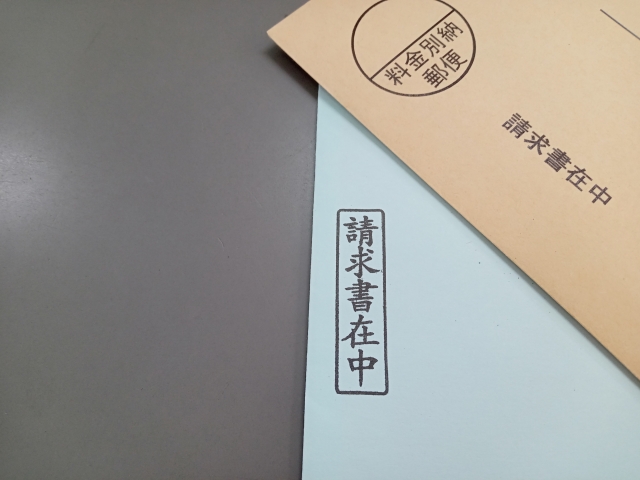
郵便料金計器とは、郵便物の重量を計測し正確な郵便料金を算出、郵便料金の支払いから印字までを自動化する専用機器です。
なお、郵便料金計器での支払いにあたっては、1ヶ月ごとの承認使用金額を設定(チャージ)し、使用分に応じた金額が月末締め、翌月20日に差し引かれます。
本来、郵便料金を計算および支払うためには、郵便局の窓口へ郵便物を持参しなければなりません。
しかし、郵便料金計器があればそのような手間をかける必要がなくなり、書類の発送業務を大幅に効率化できるのです。
郵便料金計器は、1日に処理する郵便物が多い会社・企業への導入がおすすめです。
たとえば、顧客や取引先に請求書や領収書、注文書などを郵送したり、定期的にキャンペーンやセール、イベントなどの招待状を発送したりする場合に最適です。
ちなみに、郵便物の重量を計る「はかり」も存在しますが、これは郵便料金の支払いや印字ができないため郵便料金計器とは区別されます。
郵便料金計器の平均価格帯は?
一口に郵便料金計器といっても、一度に計算・処理可能な速度や枚数、登録可能な部門数、本体サイズやオプション品の有無によっても価格帯は大きく異なります。
一般的にエントリーモデルとよばれている機種でも、およそ50〜60万円台が相場となっており、上位機種ともなれば100万円台のものもラインナップされています。
郵便料金計器は発送作業を効率化できる一方で、本体価格が高額であることから、導入にあたっては十分な費用対効果が見込めるかを検証することが重要といえるでしょう。
郵便料金計器の耐用年数

郵便料金計器の耐用年数は、税法上5年間とされています。
耐用年数とはあくまでも税法上の概念に過ぎず、経費として計上する減価償却の期間を指します。
そのため、機器本体の寿命や買い替え時期とは異なります。
郵便料金計器は毎年のように新製品が入れ替わるものでもなく、比較的寿命が長い製品といえます。
ノートPCやスマートフォンなどのように持ち運んで使用するものでもなく、基本的に一箇所に固定して使用することを想定しているため、一度購入した後は適切なメンテナンスさえ行っていれば10年、15年と長期間使用できるでしょう。
ただし、メーカーによっては将来的に交換用部品や消耗品などの生産を終了するケースも想定されます。
そのため、物理的な故障で修理が難しい場合や、交換用部品やパーツ、消耗品の生産が終了したタイミングが郵便料金計器の買い替え時期といえるでしょう。
郵便料金計器の選び方について
さまざまなメーカー、機種が揃っている郵便料金計器ですが、どういった基準で選べば良いのでしょうか。
会社の規模
郵便料金計器のなかには、部門ごとに郵便料金や発送枚数を管理する機能が備わっているものも多く存在します。
たとえば、場合は20〜30程度の部門に対応した安価なエントリーモデルから、50以上の部門に対応できる上位モデルまでさまざまです。
中小企業であればエントリーモデルで十分な場合も多いですが、大企業ともなれば上位モデルでなければ管理が難しいケースもあるでしょう。
取り扱う郵便物の大きさ
一口に郵便物といっても、請求書や注文書を送る場合と、パンフレットや資料を送る場合とでは封筒の大きさ・厚みは異なります。
また、郵便ではなく宅配便として発送しなければならないケースもあるでしょう。
発送する荷物のサイズが多様な場合、幅広い大きさに対応する郵便料金計器を選ぶ必要があります。
安価なエントリーモデルの場合、処理可能な郵便物の大きさや厚みが限られていることも多いため、各モデルを比較し検討することが重要です。
ひと月あたりの発送数
会社の規模や顧客数、取引先の数、業種などによっても郵便物を処理するボリュームは大きく変わってきます。
たとえば、ひと月に数百通といった単位であれば、エントリーモデルでも十分対応できるでしょう。
しかし、数千、数万通単位で発送するとなると、1回に処理する量も大きいため上位モデルのほうが適しているケースも考えられます。
郵便料金計器のカタログや製品仕様のなかに、1分あたりの処理数も掲載されているため参考にしてみましょう。
Quadientはさまざまな機種を用意
Quadientでは事務作業や郵送作業を効率化するためのさまざまなソリューションを提供しています。
郵便料金計器も複数の機種を用意しているため、今回はそれぞれの機種の特徴を簡単に紹介しましょう。
iX-3

https://mail.quadient.com/ja/postage-meters-mailing-systems/ix-3-series
iX-3はQuadientの郵便料金計器のなかでエントリーモデルに位置づけられる製品です。
しかし、1分あたり45通というパワフルな処理速度に加えて、標準で3kgまでのスケール、オプションで10kg、35kgまでのスケールを追加できます。
登録可能な部門数は30で、郵送業務のボリュームが多い中小企業に最適な1台です。
iX-5

https://mail.quadient.com/ja/postage-meters-mailing-systems/ix-5-series
iX-5はエントリーモデルと上位モデルの中間に位置しており、1分間に最大110通までの郵便物を処理できます。
また、封筒の厚みは最大12mmまで対応しているため、パンフレットや資料などを発送する頻度が多い企業にも最適です。
封筒を手差しで挿入するセミオートタイプのiX-5HFと、自動搬送するiX-5AFの2種類が用意されています。
iX-7

https://mail.quadient.com/ja/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%96%99%E9%87%91%E8%A8%88%E5%99%A8/IX-7
上位機種にあたるiX-7は、1分あたり最大150通の処理が可能です。
封筒の厚みは最大16mmまで対応でき、登録可能な部門数も70と充実の機能。多くの部門で郵便料金計器を共用したい大企業におすすめの1台といえるでしょう。
また、オートフィーダーが標準で搭載されているため、同一料金の郵便物であれば複数枚をセットするだけで大幅な業務効率化が実現できます。
IS-280

https://mail.quadient.com/ja/postage-meters-mailing-systems/is-280
IS-280もiX-3と同様、エントリーモデルに位置づけられる製品です。
iX-3の本体サイズは横幅670mm、奥行き390、高さが260mmですが、IS-280は横幅314mm、奥行225mm、高さ194mmとコンパクトにまとめられています。
封筒を機器に手で差し込み、スタンプを印字するタイプとなっており、1分あたりの処理数は最大18通、最大10部門の登録が可能です。
デスク上に収まるサイズのため、各部門で個別に郵便料金計器を設置したい場合におすすめの1台といえます。
まとめ
郵便料金計器を導入することで、毎月大きな負担となっていた郵便の発送作業が効率化されるばかりではなく、料金の計算ミスや過払いなども防ぐことができます。
一口に郵便料金計器といってもさまざまな機種があり、エントリーモデルから上位モデルまで機能・価格帯も多様です。
自社にとってどのモデルが適しているのか、各機種の仕様を比較しながら検討してみましょう。
