印紙税納付計器の価格帯は?導入メリット・デメリットも紹介!
請求書やチラシなどを封筒に入れて郵送する際、書類を折りたたむケースが一般的です。1枚、2枚程度の作業であればそれほど手間に感じることはありませんが、数百枚、数千枚の書類ともなると膨大な手間と時間を要してしまいます。
紙折機を使用することで、書類を折りたたむ作業を自動化でき、大幅な業務効率化につなげられます。
紙折機とは
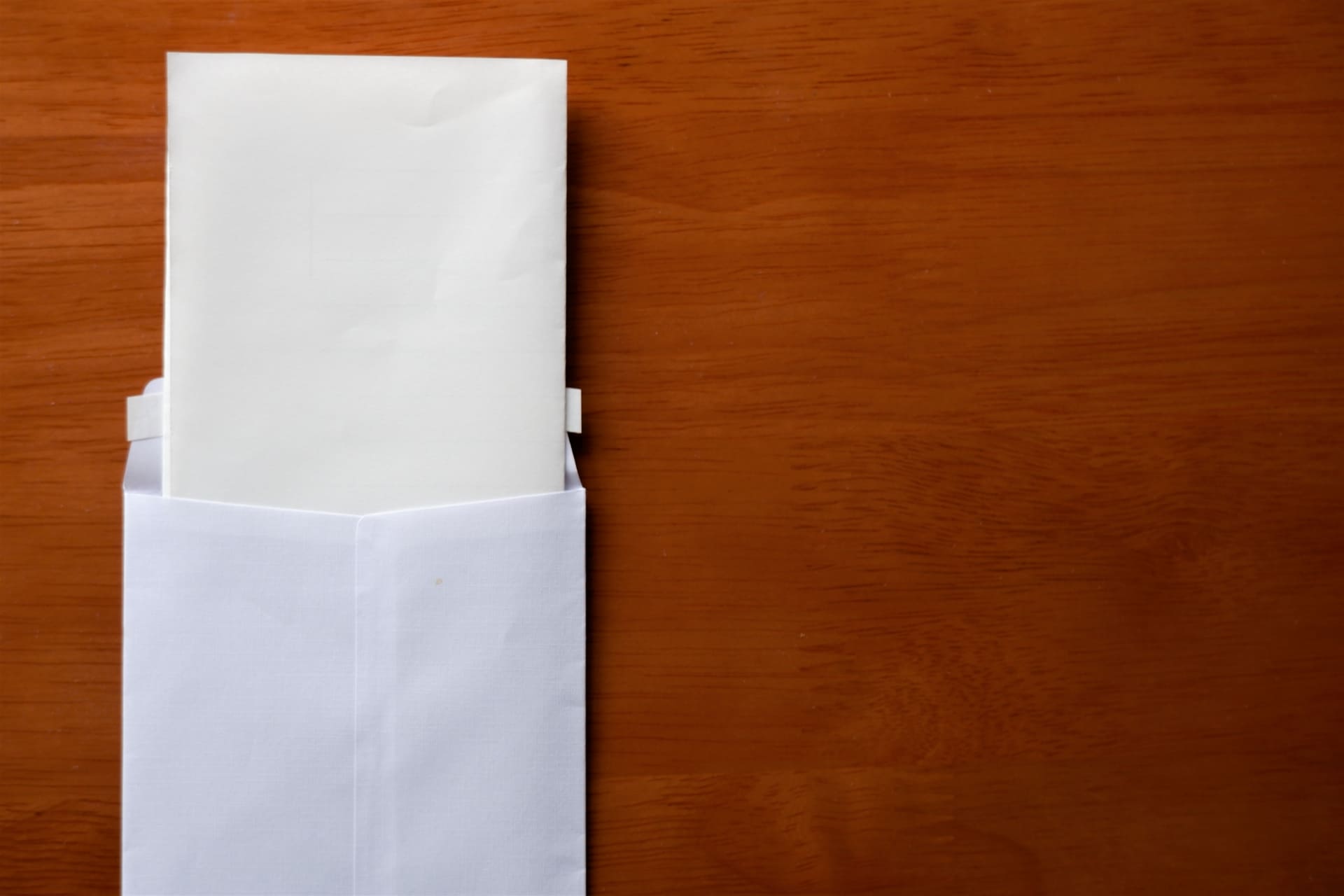
紙折機とは、書類を封筒に入れるために紙を折る作業を自動化するための機械です。
請求書や納品書、注文書、ダイレクトメールなど、さまざまな書類を封筒に入れる際、二つ折りや三つ折り、四つ折りなどに畳むケースが多いですが、手作業では膨大な時間と手間がかかってしまいます。
これらの作業を自動化し、定型業務の効率化や生産性向上につなげるのが紙折機です。
▶︎【企業向け】大量の郵便物を効率的に処理するために有効な方法とは?
紙折機で対応できる紙の大きさ
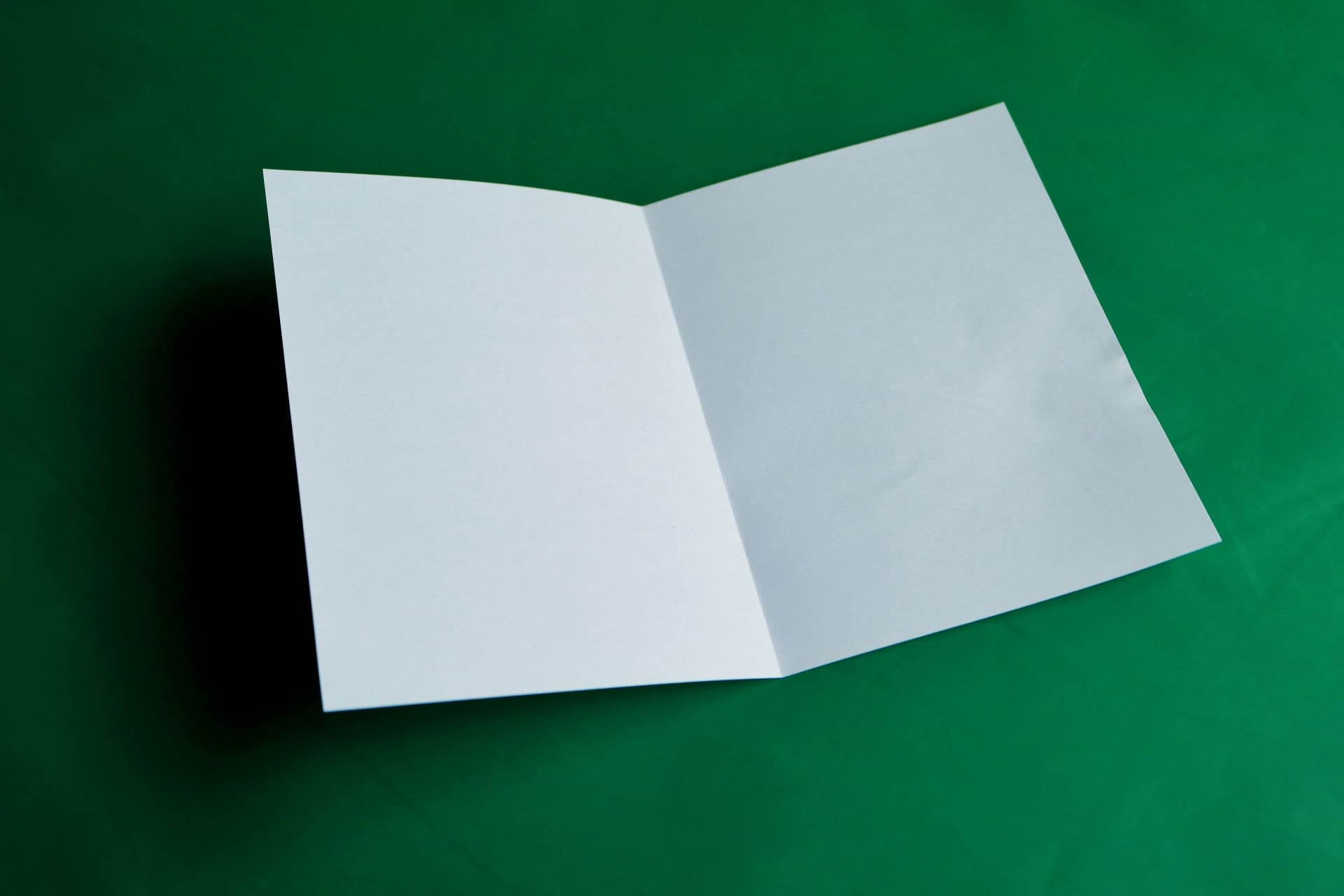
一口に書類といっても、書類の種類に応じてさまざまなサイズがあります。
多くの紙折機では、A3サイズからB6、B7サイズ程度までに対応できますが、折り方の種類によってはA5サイズまでであったり、A3サイズには対応できないなどの違いもあります。
一般的なビジネスシーンで用いられることの多いA4サイズやB4サイズなどの書類はほとんどの紙折機で対応できるため、実用面で困ることはほとんどないでしょう。
紙折機の折り方の種類
書類を封筒に入れる際には、封筒のサイズに合わせてさまざまな折り方を選択しなければなりません。
たとえば、A4サイズの大きな封筒であれば、紙を折らずにそのままの状態で入れることも多いですが、定形サイズの封筒の場合は三つ折りや四つ折りにして入れるケースが一般的です。
紙折機によっても対応できる折り方は異なり、代表的なものは以下の通りです。
- 二つ折り
- 三つ折り(外三つ折り・内三つ折り)
- 四つ折り
- 折りなし
ビジネスシーンでは三つ折りが多く用いられる傾向にありますが、三つ折りのなかにも上下交互に折り曲げる外三つ折りと、内側に収納するように折り曲げる内三つ折りの二種類があり、紙折機によっても対応できる折り方は異なります。
上位機種になるほど豊富な折り方に対応できるものが多いため、自社の用途にマッチできるかを事前に調べておく必要があるでしょう。
▶︎郵便料金計器の価格帯やメーカーによる違いは?上手な選び方を紹介
紙折機を使うメリット
紙折機を導入しなくとも、従来通り手作業で書類を用意すれば良いのではないか、と考える方も多いでしょう。
コストをかけてまで紙折機を導入することで、具体的にどういったメリットが得られるのでしょうか。
業務効率化
紙折機の使い方はシンプルで、封入する書類の束を紙折機にセットし、ボタンを押すだけです。作業の準備はわずか数分もあれば完了し、1分もあれば数百枚の書類を一律に折りたたむことができます。
手作業の場合、熟練の作業員であっても1枚あたり3〜5秒程度の時間を要するため、1分間に用意できるのは20枚から12枚程度が限界です。
このことからも、紙折機は手作業に比べて10倍以上の作業が可能であり、事務処理の量が多ければ多いほど業務効率化や生産性向上に大きな効果をもたらします。
郵便業務の品質向上
二つ折りや四つ折りなどは作業の難易度がそれほど高くないため、丁寧な作業を心がければ品質を維持することは可能です。しかし、三つ折りや観音折りなどの場合、均等に折り目をつけるのは決して簡単ではなく、二つ折りや四つ折りに比べても時間を要します。
また、きれいな折り目がついていないと封筒から書類を取り出したときにシワが目立ったり、失敗した折り目が目立ったりすることもあります。
紙折機を使用することで、すべての書類を正確に折りたたむことができ、きれいな状態で取引先や顧客に郵送できます。
コスト削減
紙折機によって業務が効率化されるということは、短時間に多くの書類を整理することにつながり、人件費の抑制にも貢献できます。
これまで事務作業を担当する派遣社員やアルバイト、パート社員などを雇っていた企業は定型的な業務に人員を割く必要がなくなり、その分を営業や企画、製品開発などの本質的な業務に割り当てることもできます。
結果として人件費の無駄がなくなり、経営効率の向上にもつながっていくでしょう。
紙折機はどんな企業におすすめ?

「ある程度の事務作業を行っているものの、紙折機を導入するべきか迷っている」という企業も多いのではないでしょうか。そこで、紙折機はどういった企業への導入が適しているのか、具体的なケースをいくつか紹介しましょう。
DMなど定期的に大量の書類を郵送しなければならない企業
多くの企業ではデジタル化が進みペーパーレスの業務に移行していますが、その一方で顧客や取引先の要望によって紙のやり取りが残っている企業も存在します。
特に、DMの発送や請求書のやり取りなど、日常的に大量の書類を郵送しなければならない企業ほど、紙折機の導入効果は高いといえるでしょう。
事務を担うスタッフが不足している企業
近年多くの企業が人手不足に悩んでおり、募集をかけてもなかなか応募者が集まらないケースが少なくありません。採用活動にも多くのコストを要するほか、採用が決まったとしても短期で退職されてしまうと採用コストが無駄になってしまいます。
紙折機を導入することで、限られたスタッフでも効率的な事務作業を実現できるでしょう。
生産性向上を図りたい企業
企業の売上や収益を向上させるためには、新たなビジネスモデルや製品開発などに着手しなければなりません。
そのためには既存業務の効率化が不可欠であり、自動化できる作業は人手がかからない方法に移行しなければなりません。紙折機も具体的なソリューションのひとつであり、定型的な業務を自動化することで生産性向上への第一歩となります。
▶︎あなたの会社にピッタリな封入封かん機はどれ?企業規模や処理数別に紹介
封入封かん機(インサーター)の導入も検討すべき?
紙折機を導入する目的は、主に業務効率化や生産性の向上などが挙げられます。しかし、書類の郵送作業は紙を折りたたむだけでなく、封筒に書類を入れて糊付けをするという作業もあります。
これらも自動化できる機械があれば、より業務効率化につながることは間違いないでしょう。
そこで、封入封かん機(インサーター)という機械を導入すれば、「書類を折りたたむ」、「封筒に書類を入れる」、「糊付けをする」といった一連の作業を自動化することができます。
書類を折りたたむ作業のなかで、均等な折り目が入れられなかったり、作業に時間を要するといった問題を紹介しましたが、封入作業においても誤って複数枚の書類を入れてしまう、封入する書類を間違う、あるいは封入漏れといったミスが起こる可能性があります。
封入封かん機を導入することで、これらの作業ミスや作業漏れを未然に防ぐことができるでしょう。
さらに、手作業による糊付けの場合、糊付けが甘く内容物が飛び出すといった事故が発生するおそれがありますが、封入封かん機では糊付け作業も均一化されるためそのようなリスクも減らせます。
Quadientのインサーターなら封入封かん作業も簡単!
書類の郵送作業を効率化するために、封入封かん機の導入を検討している方は、Quadientのインサーターをご検討ください。
ニーズに応じてさまざまな製品を準備しており、中小企業から大企業まで幅広い規模に対応できます。
DS-40i

中小企業やスタートアップ企業など、比較的規模の小さい企業におすすめなのがDS-40iです。
1時間で約1,000通の封入封かん作業を自動化でき、二つ折り、三つ折り、四つ折りが可能です。本体サイズは幅42cm、高さ54cm、奥行き65.8cmとコンパクトで、デスクやちょっとしたスペースにも手軽に設置できるでしょう。
DS-64i

中規模程度の企業で、複数の部署で共用したい場合にはDS-64iがおすすめです。
1時間に約2,500通の封入封かん作業を自動化でき、大量のダイレクトメールなども短時間で準備可能です。
二つ折り、内三つ折り、ゼット折り、四つ折りに対応でき、最大5枚までの書類折り曲げも可能です。
DS-77iQ

せっかく導入するなら性能にこだわったものを選びたい、または今後会社組織が成長し大きくなる見込みがある場合などには、DS-77iQがおすすめです。
1時間あたり3,800通の処理が可能で、二つ折り、内三つ折り、ゼット折り、四つ折りに対応。このうち、二つ折りであれば最大10枚まで同時に折り曲げることができます。
DS-85i

大企業や官公庁など、特に書類の量が多い企業・組織におすすめなのがDS-85iです。
処理性能は1時間あたり約4,000通で、Quadientの封入封かん機のなかでもトップクラスを誇ります。さらに、7インチの大型ディスプレイが採用されているため、初めての方でも直感的に操作でき、使いやすさも大きな魅力のひとつです。
内三つ折り、ゼット折り、二つ折り、四つ折りに対応し、大容量のフィーダーも搭載しているため書類の補充作業が最小限で済みます。
まとめ
書類を封筒へ入れる際に欠かせない折りたたみの作業ですが、書類の量が増えると多くの人手を要してしまいます。
特に、毎週、毎月のように膨大な量の書類を郵送している企業の場合、紙折りの作業だけでも数時間単位の工数がかかっているはずです。
紙折機を導入すれば、このような面倒な作業から解放されると同時に、空いた時間をより生産的な業務に割り当てることもできるでしょう。
また、封入作業までを自動化する封入封かん機(インサーター)を選ぶことで、さらに生産性アップにつながると期待されます。
