改定後郵便料金の一覧|郵便物の料金不足はどう対応すれば良い?
2019年、消費税率の改定とともに郵便料金も値上げされたことをご存知でしょうか。
はがきや定形郵便などは数円の値上げですが、わずかでも切手が不足していると料金不足によって正しく配達されない可能性もあります。
そこで今回は、改定後の郵便料金はいくらになったのか、一覧で紹介するとともに、郵便物の料金が不足していた場合どう対処すれば良いのかについても解説します。
郵便料金はいつ改定された?

郵便料金はこれまで、さまざまな理由によって改定されてきました。
直近で変更となったのは2019年10月1日で、消費税率が8%から10%へ引き上げとなったタイミングに合わせて実施されました。
従来と比べてどの程度の値上げとなったのか、郵便料金改定後の価格について紹介するとともに、今後郵便料金が改定される予定はあるのかについても詳しく解説しましょう。
郵便料金改定後の価格一覧

2021年7月現在、ハガキを差し出す際には63円、封書の場合は84円の切手を貼る必要があります。
現在の郵便料金は2019年10月1日から改定されたもので、それ以前はハガキが62円、封書が82円でした。
また、その他にも定形外郵便や速達、書留などの料金についても値上げされています。
今後の郵便料金改定予定
2021年7月の時点において、定形郵便やハガキなどの郵便料金については改定予定はありません。
しかし、速達料金については、2021年10月1日以降、現行の料金から1割程度引き下げとなることが発表されています。
郵便物が料金不足の場合どうなる?
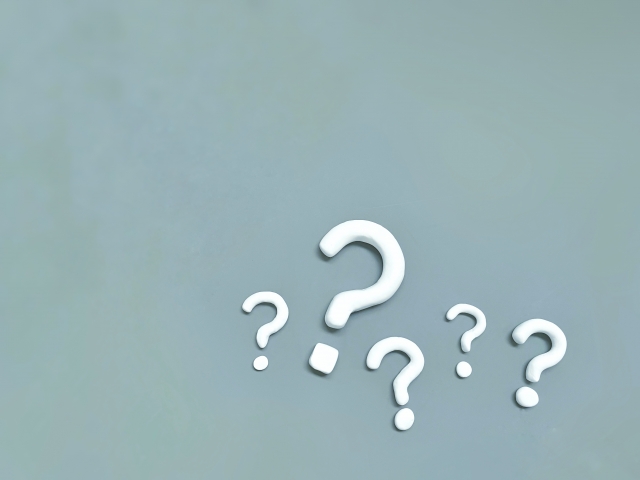
仮に郵便料金が改定されたことを知らず、従来の料金の認識のまま切手を貼ってポストに投函した場合、料金不足で正しく配達されないことが考えられます。
そのようなとき、郵便物に差出人の氏名や住所が記載されていれば郵便局から差出人へ「料金が不足しています」などのメモと一緒に返送されます。
しかし、差出人の情報が記載されていなかったり、差出人の住所と集配管轄エリアが異なっていたりする(差出人住所が東京都で、集配管轄エリアが埼玉県など)場合には、宛名に記載された受取人に配達され、受取人に対して不足額が徴収されます。
しかし、受取人によっては受け取りを拒否することも考えられ、差出人の住所も分からないと「還付不能郵便」として郵便局員によって中身が開封されるケースがあります。
開封したときに差出人の情報が判明すれば返送されますが、中身を確認しても差出人が不明の場合、以下のパターンごとに対応が変わってきます。
◆作業時間や工数削減に効果を発揮!郵便業務の効率化はどんな方法がある?
有価物で滅失・き損の恐れのある郵便物
宝石や商品券などの有価物は、ただちに売却手続きが行われ、売却代金の1割に相当する額を日本郵便が手数料として徴収します。
残りの売却代金については日本郵便で1年間保管されますが、保管期限を過ぎても請求者が現れない場合には日本郵便へと帰属します。
そのため、有価物を郵送する際には、差出人の情報を必ず記載するようにしましょう。
有価物ではない郵便物
個人に宛てた手紙など、有価物にあたらない場合には、日本郵便で3ヶ月間保管されます。
その後、3ヶ月を過ぎても請求者が現れない場合には郵便物が廃棄されてしまいます。
郵便物の料金不足の処理は郵便局員次第
もともと郵便は公共性の高いサービスであるため、仮に郵便料金が不足していた場合、郵便局員の中には配達を優先してくれるケースもあります。
しかし、速達ではなく差出人の情報も記載されている場合には、料金不足によって差出人に戻ってくる可能性も十分考えられます。
郵便物の特性や郵便局員の判断によっても状況は変わってくるため、上記で紹介した内容はあくまでも参考程度にとどめておきましょう。
もっとも重要なのは、料金不足にならないよう、あらかじめ情報を調べておくことです。
どうしても不安であれば、郵便局の窓口に持ち込んで計量のうえ正確な料金を支払うよう方法が確実です。
◆事務や総務部門の郵便業務を効率化するには?課題に対応した方法例を解決
料金不足の郵便物が届いたときは?
差出人の立場としてではなく、受取人の立場で考えた場合、ある日突然料金不足の郵便物が届き、不足分を請求されることも考えられます。
そのような場合、受取人はどう対処すれば良いのでしょうか。
不足分の料金を支払い郵便物を受け取る
あらかじめ郵便物が届くことを知っている場合には、受け取りを優先するために料金の請求に応じ、支払うことがおすすめです。
特に仕事に関係する重要な書類や、購入した商品などの場合にはいち早く受け取らなければなりません。
不足分の料金を支払う方法としては、通知はがきに不足分切手を貼り郵送する方法と、郵便局に通知はがきを持参して支払う方法があります。
不足金額が少額の場合は郵便物と一緒に通知はがきが配達されますが、100円以上の不足額がある場合には不足分の支払い確認がとれてから配達されます。
もし急ぎで郵便物を受け取る必要がある場合には、保管されている郵便局へ通知はがきを持参するとスムーズです。
受け取りを拒否する
差出人が不明であったり、到着予定のない郵便局物が料金不足によって届いたりした場合には、受け取り自体を拒否することも可能です。
通知はがきの「この郵便物は、料金が不足していますので受け取れません」という項目へチェックを入れ、サインまたは捺印のうえポストへ投函してください。
ただし、郵便物を開封してしまった場合には受取拒否ができないため注意しましょう。
差し出し後に郵便物の料金不足に気付いた場合の対処法
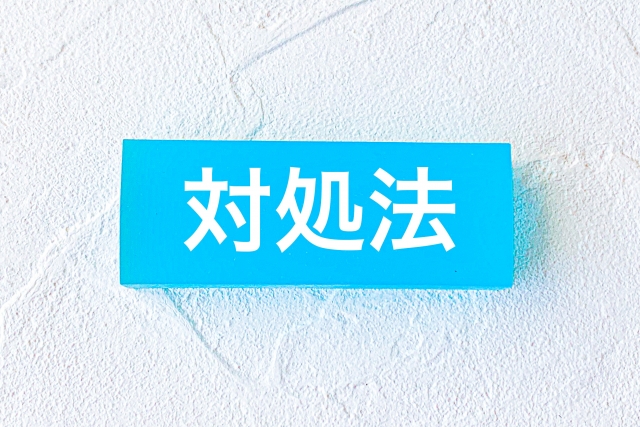
郵便物を差し出した後、自身で料金不足に気付いた場合、郵便局に対して「取り戻し請求」という手続きを行えばキャンセルが可能です。
ただし、取り戻し請求のタイミングによっては手数料が発生する可能性もあるため注意が必要です。
郵便物はポストへ投函後、エリアごとに設置されている集配局とよばれる郵便局へ集められ、その後宛先の最寄りの郵便局(配達局)へ配送されます。
郵便物がポストから集荷される前、または集配局にある段階であれば、取り戻し請求の手数料はかかりません。
しかし、すでに配達局へ到着済みで、宛先への配送待ちの状態になっている場合には、以下の手数料を支払わなければなりません。
- 配達局から取り戻し請求した場合:420円
- 配達局以外の郵便局から取り戻し請求した場合:580円
ちなみに、取り戻し請求の手続きにあたっては、本人確認書類および印鑑(認印)を持参する必要があります。
料金不足の郵便物を放置したらどうなる?
通知はがきとともに料金不足の郵便物が届いたものの、料金を支払わず受取拒否もしないまま放置しておくと、郵便局から再度通知はがきが届くことがあります。
長期間支払わずに放置していた場合、何らかの罰則がついたり、郵便局から訴えられたりといったケースは極めて稀のようですが、受取拒否をしない以上は受取人が不足額を支払う必要があるため、できるだけ早めに支払うようにしましょう。
まとめ
郵便料金は消費税増税などのタイミングで改定されており、それに気づかないまま切手を貼ってポストに投函してしまうと、料金不足によって相手先に届けられない場合があります。
また、受取人に対して不足額が請求されてしまうため、当事者間でのトラブルやクレームに発展する可能性も考えられます。
今回紹介した内容を参考に、郵便物を発送する際には十分注意して過不足なく料金を支払うようにしましょう。