毎日のように大量の書類を郵送する企業や部署では、書類のサイズや重量に応じて料金を計算し、切手を貼ったり郵便局の窓口で手続きを行うのは面倒な作業です。
バックオフィス部門の生産性アップを実現するためにも、従来の書類発送作業を効率化することは大きな課題といえます。そこで役立つ方法のひとつとして、「料金後納郵便」があります。
今回の記事では、料金後納郵便とはどのような制度なのか、利用するための条件や手続き方法、メリットとデメリットなども含めて詳しく解説します。

料金後納郵便とは?

料金後納郵便とは、郵便物の差し出しにかかった料金を1か月分まとめて納付できるサービスです。
通常、郵便物の差し出しにあたっては、はがきや封書へ1通ずつ切手を貼り付けなければなりませんが、料金後納郵便の場合は切手の代わりに「料金後納郵便」という専用のラベルを表示することで切手を貼り付けることなく郵送が可能です。
ただし、料金後納郵便を利用するためにはいくつかの条件があります。

<利用条件>
- 郵便物・荷物を毎月50通(個)以上差し出すこと
- 事前に取扱郵便局からの承認を受けていること
※「荷物」のなかには「ゆうメール」および「ゆうパケット」は含まれません。なお、国際小包の場合は1か月あたり10個以上、EMSは4個以上で条件の対象となります。
なお、上記以外の条件として、1か月に差し出す見込みのある郵便物・荷物に応じた概算金額の2倍以上にあたる担保の提供が求められることがあります。
これは必ずしもすべての事業者が対象となるものではありませんが、もし担保の提供が求められた場合には以下のいずれかに該当するものを提供します。
- 現金
- 日本郵便が定める有価証券
- 日本郵便が定める保証
- 金融機関の保証
- 日本郵便が定めた会社の保証
料金後納郵便のメリット・デメリット
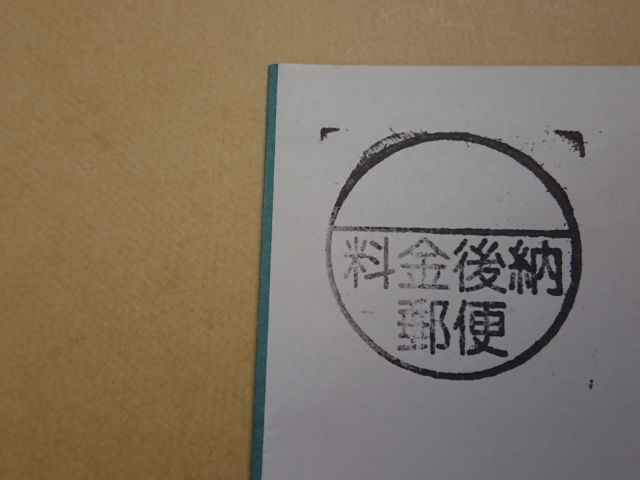
一般的な郵便ではなく、料金後納郵便を利用する際にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
また、同時にデメリットとして考えられるポイントについても紹介します。
料金後納郵便のメリット
①経理作業の効率化
郵便物や荷物の発送にあたっては、企業においては「通信費」や「荷造運賃」という項目で経費を計上しなければなりません。
しかし、郵便物の量が多くなればなるほど経費として処理すべき量も増え、事務処理が煩雑化します。また、はがきや切手を社内でストックしている企業も多いと思いますが、これらの在庫管理にも手間がかかるもの。
しかし、料金後納郵便であれば郵便物を差し出すごとに経費申請が不要であり、従業員が個別に領収証などを提出する必要がありません。
また、はがきや切手をストックしておく必要もなく、在庫管理の手間も省けます。
②発送作業の効率化
封書を差し出す際、通常であれば計量を行い、それに対応した金額の切手を貼り付ける必要があります。
また、荷物の発送は郵便物の窓口へ持参し、その場で料金を支払わなければなりません。
しかし、料金後納郵便の場合は「料金後納郵便」のラベルを印字した封筒に入れてポストに投函するだけで発送が完了します。
封書や荷物の大きさ・重さに関係なく郵便局側で料金を計算し、1か月ごとに合計金額を算出してくれるため、発送作業が大幅に効率化されます。

③経費削減
料金後納郵便では、同一種類の郵便物を1か月あたり3,000通以上差し出した場合、10%以上の割引を受けられる「月間割引」というサービスがあります。
月に5,000通の場合は15%、10,000通以上の場合は20%の割引を受けられるため、経費削減につながります。
料金後納郵便のデメリット
①少量の発送には不向き
利用条件でも紹介したとおり、料金後納郵便は毎月50通以上の郵便物や荷物を差し出す場合にのみ適用されるため、小量の発送には不向きといえます。
また、企業や業種によってはセール期間などに大量のダイレクトメールを差し出す場合もあるでしょう。
しかし、それ以外の期間ではほとんど郵便物を差し出すことがない場合、料金後納郵便の対象とはなりません。
②事前に承認を受けなければならない
料金後納郵便は利用を開始したいときにすぐに始められるものではなく、管轄郵便局からの事前承認を得る必要があります。
事前承認の手続きにあたっては、「料金後納承認請求書」や「後納郵便物等他局差出承認請求書」など複数の書類を記入し取扱局へ申請しますが、承認が下りるまでに日数を要するため、即日利用可能となるわけではありません。

③担保の提供が必要な場合がある
申請者によっても条件は異なりますが、申請時に担保の提出が求められるケースがあります。
1か月あたりの概算額の2倍以上の現金または有価証券などを差し出す必要があるため、初期費用として一時的に支払う額を用意しておかなければなりません。
料金後納郵便の手続き方法
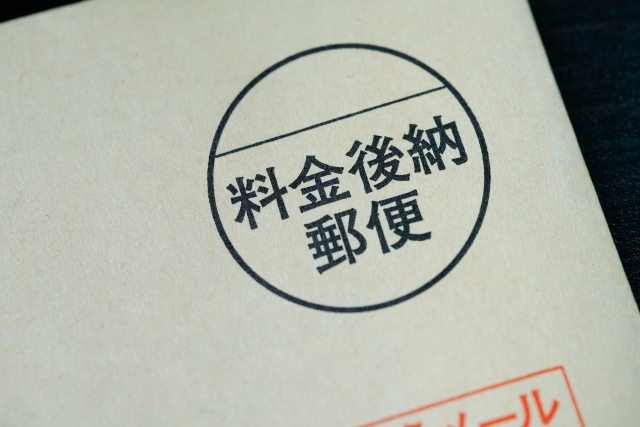
料金後納郵便の利用開始にあたっては、以下の流れで手続きを行い事前承認を得る必要があります。
1.郵便局の窓口で相談
料金後納郵便での差し出しが可能な郵便局は、集配業務を行っている郵便局に限られます。
もし対象の郵便局が分からない場合、最寄りの郵便局の窓口へ出向き「料金後納郵便の利用開始手続きをしたい」旨を相談しましょう。
対象の郵便局がどこかを教えてくれるほか、手続きに必要な書類、その他細かな申込条件なども教えてくれます。
2.書類の準備・申請
郵便局の窓口で必要書類を受け取り、必要箇所を記入します。
「料金後納承認請求書」や「後納郵便物等他局差出承認請求書」など、書類にもさまざまな種類が存在し、郵便局では用紙を準備していますが、日本郵便のホームページからWordファイルとしてダウンロードすることも可能です。
なお、書類の申請時に担保の提出が求められた場合、担保額に相当する金額が貯金されているゆうちょ銀行の通帳および印鑑も提出します。

3.「ゆうびんビズカード」と「後納郵便物差し出し票」の受領
申請が正常通りに完了すると、郵便局から「ゆうびんビズカード」と「後納郵便物差し出し票」が届きます。
「ゆうびんビズカード」とは、郵便局で荷物の差し出し手続きを円滑化するための利用者向けのカードで、「後納郵便物差し出し票」は料金後納郵便を差し出す際に添付する書類です。
これらを受領した時点で料金後納郵便は利用可能な状態となります。
なお、専用ケースに入れて郵便物を差し出す「後納ポストイン」を利用すれば、郵便局の窓口へ出向くことなくポストに投函できます。
料金後納郵便の表示方法
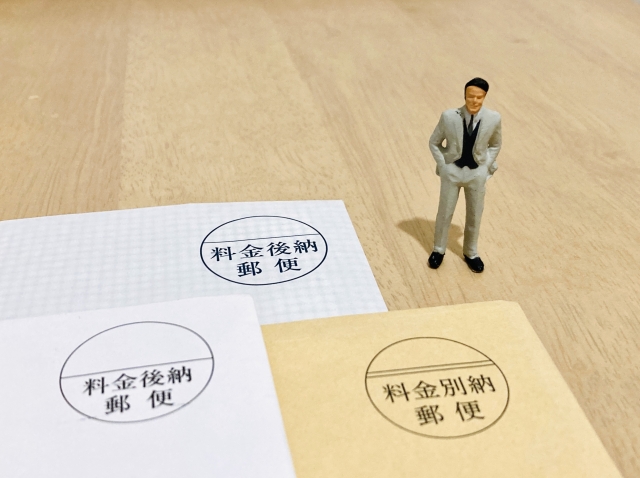
引用:https://www.post.japanpost.jp/send/fee/how_to_pay/deferred_pay/index.html
料金後納郵便では郵便物や荷物の左上または右上部分に「料金後納郵便」という表示をしなければなりません。
表示の形状は丸形と四角形があり、いずれも上部に差出事業所名、下部に「料金後納郵便」を記載します。
差出事業所名とは取扱郵便局のことで、たとえば銀座郵便局へ差し出す場合には「銀座局」と記載します。
また、四角形のラベルの場合は「料金後納郵便」の下部分に自社の社名や広告などを記載することも可能です。

郵便料金計器を使えば更に効率的に
クアディエントジャパンの郵便料金計器を採用すれば後納払いも可能になり、50通以上の差出と言う制限も無く、郵便物の管理が全体的に効率的になるメリットがあります。
郵便料金計器導入の主なメリット
- 切手の購入・管理が不要
- 作業時間の大幅軽減
- 郵便費の支払いは月一回
- ポストに投函が可能
- 企業の広告も挿入可
- 毎月〇〇通以上利用といった利用条件がない
- 差出表の作成が不要になる
- 窓口持ち込みの手間がなくなる
上記メリットから、忙しい仕事の合間に封筒の重さを測ったり切手を貼ったりする作業が、ほぼ全て自動化するので本業に集中できます。
郵便料金は自動計算、部課別の集計も簡単確実で、使った分は月ごとに後払いができるので、郵便料金計器はおすすめです。

料金後納郵便の手続きのまとめ
今回紹介してきたように、料金後納郵便は経理作業や書類発送作業の効率化、経費の削減といったさまざまなメリットが得られる制度です。
しかしその一方で、毎月50通以上の書類を発送しなければならなかったり、手続きが煩雑などのデメリットがあることも事実です。
郵便料金計器であればその部分も解決できる事が多いので、まずは資料請求でメリットを再度確かめてみてはいかがでしょうか?
事業規模や事務作業の工数なども考慮しながら、自社にマッチした制度なのかをあらためて検討したうえで活用してみましょう。

