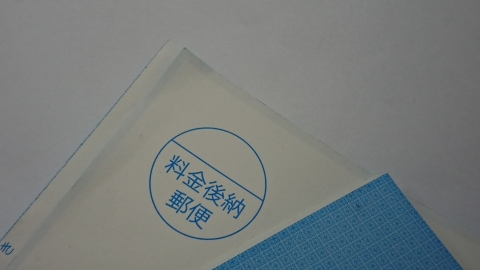取引先や顧客へ毎日のように大量の郵便物を発送しなければならないとき、事務作業の人手が足りず頭を悩ませている企業も多いのではないでしょうか。
また、自社宛てに届いた郵便物の仕分けや処理に手間がかかっているケースもあるかもしれません。
このように、大量の郵便物を処理するためにはどういった方法が有効なのか、具体的な方法やツールもあわせて紹介します。

発送の準備作業を効率化する方法
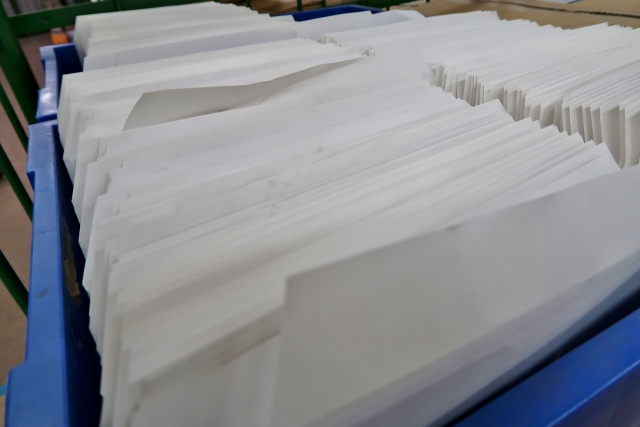
自社から大量の郵便物を郵送する際には、郵送したい書類を封筒へ封入し、封をとじるという作業が必要です。
1通あたりの作業はそれほど手間に感じることはありませんが、一度に数十通、数百通以上の差し出しが必要な場合には、発送の準備作業だけで多くの時間と手間を要します。
これを効率化するためには、以下のような方法が考えられます。

封入封緘機(インサーター)の導入
封入封緘機(インサーター)とは、書類を折りたたんで封筒へ封入し、封筒の糊付けをするまでの作業を自動化する機器です。
封入したい書類と封筒を複数枚セットするだけで、数十通、数百通の郵便物を短時間で処理できます。
特に、セールやキャンペーンなどを実施する際、多くの顧客にダイレクトメールを発送しなければならないときもあるでしょう。
そのような場合でも、封入封緘機を使用することで人手をかけることなく短時間での準備が可能です。
封入封緘機を活用すれば、作業効率化が図れるだけでなく、糊付けの漏れやムラをなくしたり、封入すべき書類を忘れてしまったりといった作業品質の低下も防ぐことができます。
▶︎あなたの会社にピッタリな封入封かん機はどれ?企業規模や処理数別に紹介
郵便管理ソフトウェアの導入
複数の宛先へ異なる内容物を差し出さなければならないケースもあるでしょう。たとえば、A社には請求書、B社には納品書、C社には見積書を差し出すといったケースです。
一度に差し出す郵便物が少量かつ宛先の数も限られている場合には手作業でも問題ありませんが、これが数十通、数百通といった単位になるとミスが生じやすくなります。
そこで、郵便管理ソフトウェアを活用することにより、作業の効率化と品質向上が実現できます。
封入指示マーク(OMR)や一次元バーコードを書類の一部分に印刷することで、封入封緘機でその情報を読み取り、宛先に応じた書類を自動的にピックアップし、スピーディーな準備作業を実現できます。
▶︎書類発送業務を効率化し生産性アップに貢献する郵便管理ソフトウェア
発送作業のアウトソーシング
現在、多くの企業は人手不足が深刻化しており、そもそも郵便物を処理するための人材が確保できないという企業も多いでしょう。
さまざまなツールや機器を導入しても、自社のリソースだけで解決が難しい場合には、一連の発送作業そのものを外部の企業に委託する方法もあります。
定型的な業務を委託することにより、自社の従業員はより専門的な業務に専念することができ、生産性アップも期待できるでしょう。

各種郵便制度を活用して発送作業を効率化
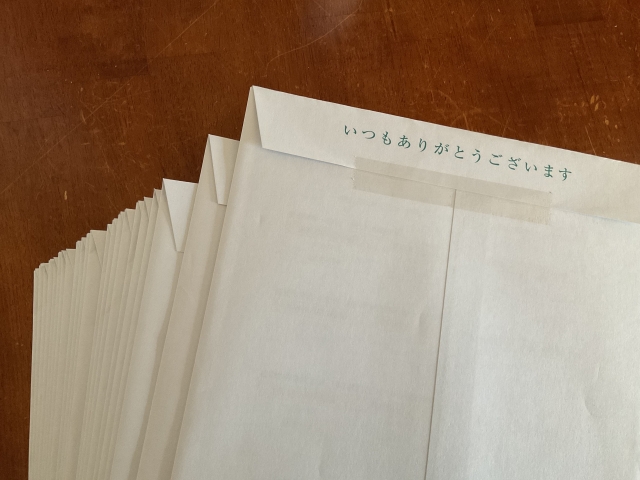
郵送の準備ができたら、1通ごとの重量を測定し、それに対応した金額分の切手を貼り付けてポストに投函または郵便局の窓口に差し出すという作業が必要です。
しかし、毎日のように大量の郵便物を発送するとなると、発送作業だけで多くの時間と手間を要してしまいます。
大量の郵便物を発送する作業を効率化したい場合には、日本郵便が提供している各種郵便制度を活用する方法があります。
料金別納
日本郵便では、大量の郵便物を発送する企業や事業者などに対し、切手を貼る代わりにマークを印字し、郵便料金をまとめて支払えるサービスを提供しています。
「料金別納」はそのサービスのひとつで、以下の条件を満たした場合に利用できます。
- 差し出す郵便物が同一料金であること
- 同時に10通以上の郵便物を差し出すこと
- 差出時に郵便料金を現金または切手で支払うこと
料金別納として差し出すと、切手を貼る部分に「料金別納郵便」というスタンプが押されます。
料金後納
料金別納よりもさらに効率化が期待できるのが、料金後納というサービスです。
料金別納は差出時に郵便料金を都度支払う必要がありますが、料金後納の場合は1ヶ月分の料金をまとめて支払うという仕組みです。
専用ケースに入れた郵便物をそのままポストに投函できるため、毎日のように郵便局へ足を運ぶ必要がなくなり、発送作業の手間が大幅に減るでしょう。
ただし、料金後納を利用する際には、事前に取り扱い郵便物へ問い合わせのうえ、個別に承認を受ける必要があります。
料金計器別納
料金後納をさらに便利に効率的に活用するには、料金計器別納というサービスがおすすめです。
郵便料金計器とよばれる専用の機器を購入し、それを郵便局へ持ち込んで承認を受けることで、郵便料金の計算および支払い、「郵便料金」マークの印字までも自社で完結できるようになります。
これにより、専用ケースに入れなくても郵便物をそのままポストに投函でき、発送作業のさらなる効率化が実現できるでしょう。
自社宛ての大量の郵便物を効率的に処理する方法

自社から郵便物を発送するだけでなく、自社宛てに届く大量の郵便物の処理に頭を悩ませている企業も少なくありません。
効率的に郵便物を処理するためにはどういった方法が有効なのか、3つの方法例を紹介しましょう。
郵便ボックスの設置
部署の数が多い企業では、届いた郵便物を各部門や担当者ごとに仕分けをして配布しなければなりません。
しかし、郵便物の量が多いと仕分けに手間がかかるほか、誤って他部署の郵便物が紛れ込んでしまうこともあるでしょう。
このようなミスをなくし効率的に仕分け作業をするためには、郵便ボックスを設置することで解決できる場合もあります。
郵便ボックスは総務部門などにまとめて設置する方法もあれば、規模の大きい企業はメール室を設け、その中に郵便ボックスを設置しているケースも少なくありません。

開封機の導入
郵便物の処理においては、仕分け作業以外にも封筒の開封に手間がかかることもあります。
特に、毎日のように取引先から契約書類や請求書、見積書などが届く部門では、1通ずつ丁寧に開封するのに時間を要します。
また、スピードアップを図るために急いで作業を進めてしまうと、中身の書類を破損するおそれもあるでしょう。
このような開封作業を効率化するためには、開封機の導入もおすすめです。
サイズの異なる複数枚の封筒でも、開封機にセットすれば自動的に開封でき、中身の書類を破損する心配もありません。
郵便ボックスのそばに開封機を設置しておけば、郵便物を受け取ったその場で開封作業もでき、業務効率化に役立てられるでしょう。
▶︎レターオープナーの電動と手動のメリット・デメリットや価格帯を紹介
▶︎クアディエントの郵便料金計器で総務や経理のお悩みを解決!詳細はこちら
大量の郵便物を効率的に処理し生産性を向上させよう
自社から郵便物を差し出すとき、または自社に届いた郵便物を処理する際には、さまざまな工夫によって効率化・自動化することができます。
1通あたりの作業はそれほど手間がかからないように見えても、郵便物の量が増えると業務の負荷が増大し生産性が下がってしまうこともあるでしょう。
このような悩みを解消するためにも、今回紹介した方法を参考に効率化を進め、生産性向上に役立ててみてください。