封筒で案内状や重要書類を送る際のマナー「封緘」とは? (Copy)
契約書や営業情報が記載された書類、さらには式典やイベントなどの招待状・案内状を送付する場合、相手に対して失礼のないよう「封緘」に関するルールやマナーを把握しておくことが大切です。
本記事では、封緘とはどういった作業なのか、封緘の仕方や知っておきたいマナー、封緘作業を効率化するための方法もあわせて紹介します。
封緘とは

封緘(ふうかん)とは、一言でいえば「封をとじること」を指します。
封筒に書類を入れてポストに投函する際、封をとじないままだと輸送時に書類が飛び出してしまうため、封緘作業は必須です。
書類などの内容物を安全に配送すると同時に、書類が配達されるまでの過程で第三者に見られていないことを証明するためにも、封緘は重要です。
封緘の歴史
封緘の「緘」という字は、細い紐で縛ってとじる”とじひも”のことを指しています。そのため、封緘は本来、紐でとじる方法が広く採用されてきました。
しかし、時代の変化とともに封緘の方法も変わってきており、現在では糊づけをしたり、セロハンテープやシールなどを用いたりする方法が一般的です。
また、海外では古くからシーリングワックス(封蝋)とよばれる蝋の一種を溶かして封をすることが多く、一口に封緘といってもさまざまな方法があるのです。
封緘の仕方
封緘の方法や仕方は厳密に決まっているものではなく、封筒から中身が飛び出ないように封ができれば問題ありません。封筒の大きさに応じて書類を折り曲げて封入した後、封入口を密封します。
たとえば、上記でも紹介したように、セロハンテープやシールなどは手間がかからない方法であり、短時間に大量の封緘作業をしなければならない場合に有効でしょう。
知っておきたい封緘のマナー
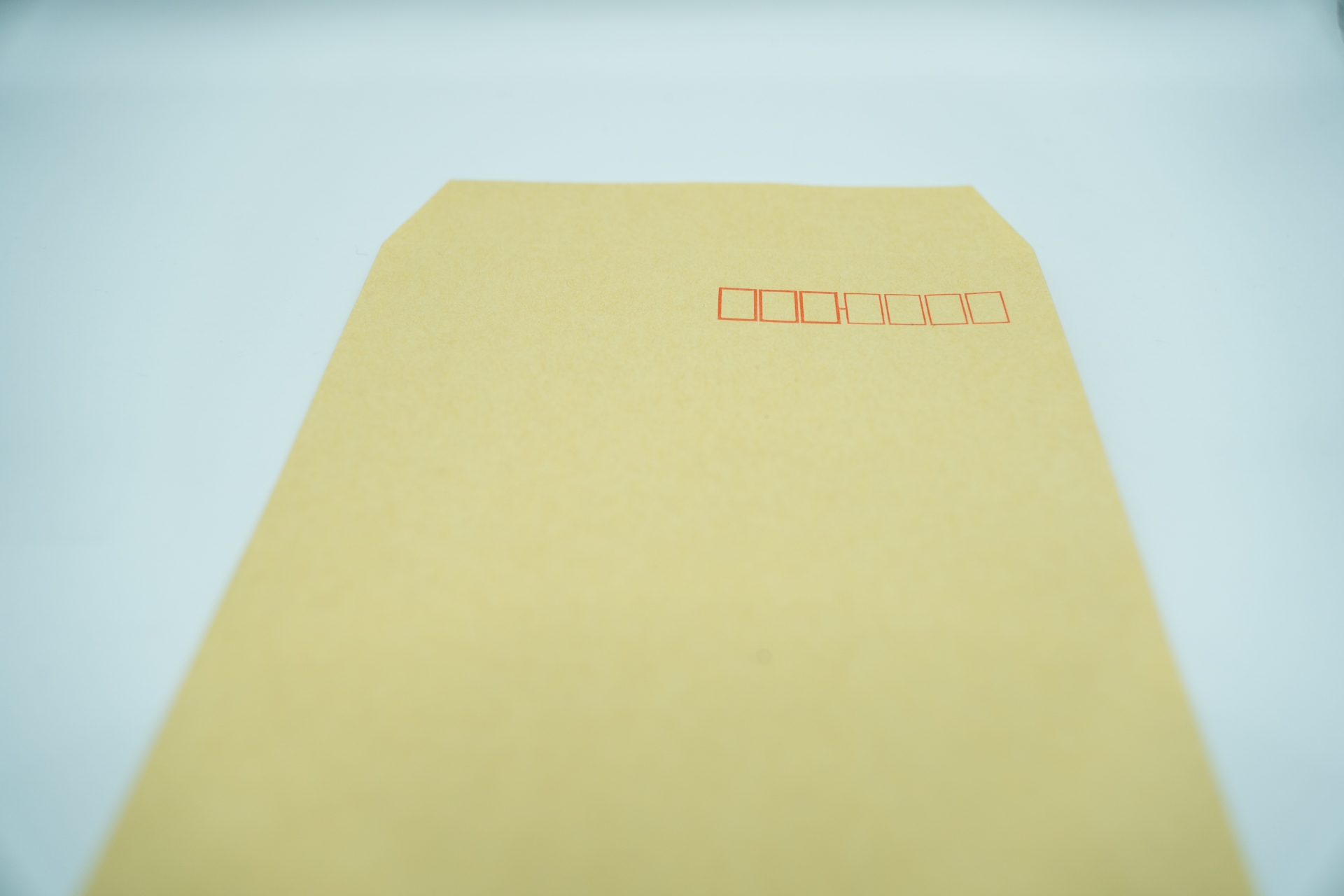
封緘の作業は決して難しいものではありませんが、封書を差し出す相手先や封入する文書の種類によってはマナーを覚えておく必要もあります。
封緘にはどういったマナーがあるのか、いくつか代表的なものを紹介しましょう。
機密性の高い文書には糊付けをする
セロハンテープで封緘をする方法もあることを紹介しましたが、これはあくまでも一般的な書類やプライベートの用途に限られます。
セロハンテープの場合、封筒から剥がしても跡が残りづらく、一旦剥がした後に新しいテープを貼っても気付かれにくいためです。
特に営業情報や顧客情報など、機密性の高い文書を送る際には、セロハンテープではなく必ず糊付けをしておきましょう。
封の継ぎ目部分には封字を記載
重要書類を糊付けした後は、必ず「封字」を記載しておきましょう。
封字とは、封筒をとじた継ぎ目部分に記載する文字のことで、一般的には「〆」や「緘」などが用いられます。
これらの文字を手書きで記載することもあれば、専用の印鑑で封字を残しておくケースもあります。
なお、結婚式をはじめとしたビジネス用途以外の慶事では、「寿」や「賀」などが用いられます。
封字にはそれぞれ意味があるため、場面に応じて使い分けることが大切です。
慶事の招待状には専用のシールを使用する
結婚式など慶事の招待状を送付する際には、「寿」や「賀」などの封字を記載しますが、手書きではなく封筒の裏面に金色のシールを貼って封緘をすることも多くあります。
シールの形状は丸いものが多いですが、扇状や梅の花をかたどったものなど、さまざまな種類が存在します。
慶事用のシールは、書店や文房具品を扱うお店などで販売されていることが多いです。
封字の種類と意味

封字には複数の文字が存在し、場面に応じて使い分けることが大切であると紹介しました。
具体的にどういった種類があるのか、それぞれの意味もあわせて解説しましょう。
「〆」・「締」の意味
〆は「締(しめ)」を簡略化した文字であり、もっとも広く使われている封字といえるでしょう。
簡略化せず「締」と表記することも可能ですが、これが用いられるのは一般書類やプライベートの場面が多く、契約書などの重要文書や機密性の高い文書には使用しないのがマナーとされています。
「緘」の意味
「〆」または「締」を使用しない重要文書・機密性の高い文書に対しては、「緘」という封字を使用します。
「〆」や「締」の封字は手書きで記載することが多いですが、「緘」は封緘印とよばれる専用の印鑑を使用することが多くあります。
「寿」・「壽」の意味
結婚式などの招待状に用いられるのが「寿」という封字です。
なお旧字体の「壽」という文字を使用しても問題ありません。
「賀」の意味
結婚式以外のお祝い事や、それにともなう挨拶状、お祭りごとで用いられるのが「賀」という封字です。
「蕾」・「つぼみ」の意味
「蕾」は差出人が女性である場合にのみ使用できる封字です。
ひらがなで「つぼみ」と書くことも可能ですが、この場合は必ず縦書きで記載しましょう。
封緘作業を効率化する方法

封緘作業は一つひとつの工程を見ると決して難しいものではありません。しかし、たとえば取引先や顧客に対して数十通、数百通といった大量の封書を発送するとなると、手作業の場合多くの時間と労力を要します。
そこで、封緘作業を効率化するためにはどういった方法が効果的なのでしょうか。
封緘印を使用する
大量の封筒に1通ずつ封字を記載するのは時間と手間がかかります。「〆」のような簡易的な封字であれば楽に作業が進みますが、「締」や「緘」のように画数が多いと作業効率は低下するでしょう。
そこで、封緘印を使用することにより、1通あたりの作業を簡素化でき作業効率化が期待できます。
封緘機を導入する
封緘作業でもっとも多くの手間と時間を要するのが、封筒の糊付けです。
1通ごとに手作業で糊付けをするのは大変な作業で、急いで作業を進めると糊付けにムラができることもあります。
その結果、糊付けが不十分で重要書類が封筒から飛び出してしまったり、書類と封筒が糊で密着し取り出しづらくなったりすることもあるでしょう。
そこで、封緘機を導入することにより、このような問題を解消し作業の大幅な効率化が期待できます。
封緘機のなかには自動給紙装置を搭載したものも多く、複数の封筒をセットするだけで自動的に封緘作業を完了できます。
また、封緘作業だけでなく、書類を折り曲げて封筒に入れる「封入作業」にも対応できる装置もあり、これは「封入封緘機」とよばれます。
宛先ごとに異なる大量の書類を封入・封緘しなければならない場合でも、OMRやバーコードなどで情報を読み取り、宛先ごとに作業を自動化できる装置もあります。
まとめ
封筒に入った書類を安全に届けるためにも、封緘は欠かせない作業のひとつです。
作業そのものは決して難しいものではなく、ルールやマナーさえ把握しておけば誰にでもできる作業です。
ただし、特に機密性が高い文書や案内状などを送付する場合には糊付けが必須であり、封字の画数も多いことから作業効率化が重要な課題となります。
ビジネスの場面で封緘作業を効率化するためにも、封緘機の導入をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
